まずはお気軽に
ご相談ください
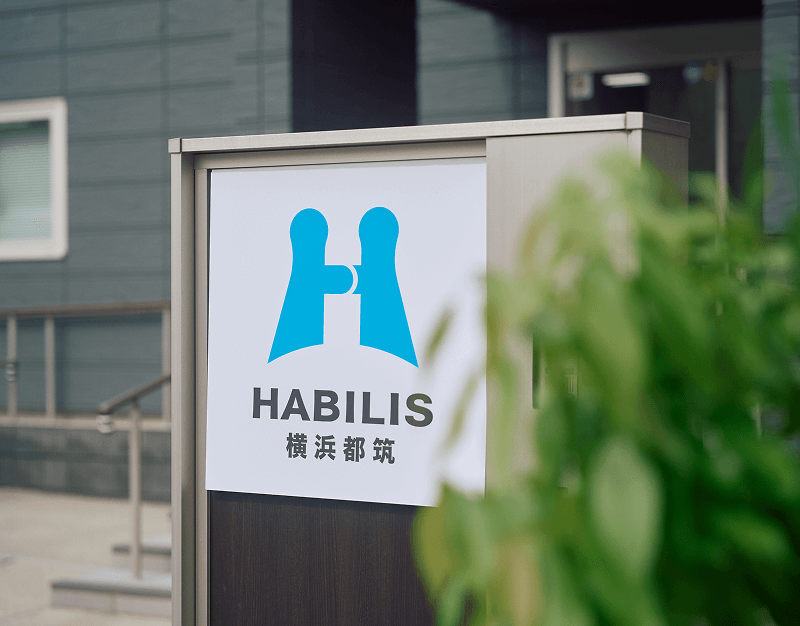
-
受付時間:月~金 10:00~17:00
(定休日、土日を除く)

撮影を企画していただきありがとうございました。吸引が多くて大変なので、手伝ってもらいながら、素敵な七五三の写真をプロの方に撮ってもらえて最高です。お友達と一緒に撮れたのも可愛くて、親の方がはしゃいじゃいました(笑)
熱を出すことが多いのに、不思議と大事な行事の日には参加できていて、本当に成長を感じます。本人も「今日はディズニー!楽しそう!」ってよくがんばってくれます。
一番は安全に、臨機応変に、たくさんの経験をさせてくれることです。体調の波が大きいので、一般的な保育園やメディカルショートだけでは埋まらない“狭間”がある。健康と経験、その日のバランスに合わせて柔軟に寄り添ってくれる安心感があります。
今は短期入所、保育園、メディカルショート、居宅訪問型の支援、そしてハビリスを利用していて、それぞれ役割が違うから、組み合わせて使えるのが助かります。
スタッフと親の距離が近いところですね。娘を送りに行ったときに私も店舗で雑談したり、一緒に新しい経験をしたりできる。核家族で頼れる人が少ない中、ハビリスのスタッフさんと一緒に出かけられた体験は本当に大きいです。夫も、私だけが言っても無理だったディズニーを、スタッフさんが一緒なら「行けるかも」と思えた。
あとは、チームで情報が共有されていることを感じます。
ハビリスは「チームで共有されている感じ」がすごく伝わります。病棟だと人が増えるほど、前に話したことが通じず同じ説明を繰り返す——そんな不信感や警戒心が生まれがちですが、ここではそれがほとんどない。スタッフ間のスキルの差も小さくて、「この人には言わないでおこう」と思う場面があまりありません。全体で底上げされている印象というか、何か工夫されているのでしょうか。
いまのお話を聞いて、私が感じていた“チームワーク”の正体が分かった気がします。共有の仕組みと、支え合う文化があるから、私たちも安心して相談できるんですね。
人が増えても相談しやすいし、忙しさを気にせず連絡も送れてありがたいです。

最初は本当に「居場所がない」ところからのスタートでした。役所に聞いても古い情報だったり、結局親が勉強しながら生活を構築していくしかなかったです。訪問看護師さんも「誰に繋げたらいいのか分からない」と言います。そんな中でハビリスに出会えたのは救いでしたね。
また、娘のための支援なので、入院すると支援が中断してしまい、家に一人でいる孤独感も辛かったです。ある時、娘が地域の病院と大学病院とでたらい回しになったことがあります。幸い入院できましたが、どうしたらよかったのか必死で、検査の紙を持ってハビリスへ相談に行きました。すぐに解決できなくても、直接話を聞いて、それぞれの経験からアドバイスをくれた。
「一緒に考えてくれること」が大事なんですよね。そういう機関って実はなかなかなくて、“困ったら相談して”とは言ってくれるけど、実際いきなりはハードルがあるし、別の問い合わせ先を案内されて“なんか違う“こともある。だからこそ、ハビリスのように、話せると思えて、話を聞いてくれて、実際に一歩動いてくれる存在は貴重だと思います。
たとえば、娘がゼロゼロして呼吸が苦しい時期に、姿勢が楽になるように椅子を調整してくれたこともあります。病院に相談しても解決策には至らなかったけど、ハビリスは実際に形にしてくれた。入院が長引く中、「病院に持ち込んで使ってください」と言ってくれて、いざ持って行くと主治医も看護師さんも「これはいいですね」と好評でした。
正直、困らせてしまうかもと言えないこともあるけれど、会う頻度が多いので何気ない会話の中でぽろっと話せる。その一言から助けてもらえることが本当に多いです。
気切後にようやく安定して登園できるようになり、ハビリスが一緒に入って環境を整えてくれました。
「できることはさせてあげたい」という“熱意”がある保育園だと思います。すると次は、“スキル”も必要になるんですね。やりたいけどやり方がわからない、そんな保育園とハビリスが繋がってくれたことで、最強の体制になったと感じています。
「以前関わったことがある」って言える人が増えれば、保育の現場でも自然にインクルーシブが根づくと思うんです。だから、保育園に通うなら“保育所等訪問”は絶対セットでおすすめしたいです。
そんな保育園ですが、3歳になるとき「もう抱っこはしません」という話がありました。
座るのに介助が必要なだけなのに、保育園ではそれが“特別扱い”で“ずるい”になるのか言葉にできずにいました。でも、今では先生たちが自然に抱っこして活動に参加させてくれています。周りの子どもたちも“ずるい”とか全然言わない。むしろ理解してくれて、園全体が少しずつ変わっていくのを感じます。
保護者の方々にも、娘のことを紹介するお手紙を配布させてもらいました。
ある日、園の門で男の子に「病気なの?」と聞かれ、「眠いだけだよ」と答えたら、後日「病気のことを隠さないでほしい」と園から言われて……私としては、娘を“病気の子”として生活している感覚はなかったんです。そうした誤解もあって、きちんと伝えようと思いました。
お手紙を出したら、声をかけてくれるお母さんが増えて、「○○ちゃんが一緒にいることで、子どもたちにとっても良い経験になっている」と言ってもらえた。子どもたちも怖がらずに手を握りに来てくれたりして、純粋で優しいんですよね。偏見がなくて、本当に大事なことを自然にわかってくれていると感じます。
まず、本当に案内役がいないんです。だから、早い段階でSNSが主流になる。
病院を出てから、とりあえずネット検索して児発のホームページを探すけど、発達障害向けばかりで通える場所が見つからない。個人のブログやインスタに行きついても、あくまで“キラキラした一部の切り取り”なのに、「障害児でも楽しく暮らしてます」「障害児ママでも自己実現してます」と、タフで前向きなお母さんが多く思えてくる。自分もそうならなきゃいけないような気がして、逆に追い詰められる瞬間もありました。
やっぱり、SNSやネット検索だけだと、どこかで“罠”にはまる。対面で話せる関係がないと、心がどんどん閉じていってしまうんです。そういう意味でも、ハビリスで横のつながりができて、他のお母さんの姿を知る機会が増えたことは本当にありがたかったです。「自分だけじゃない」と思えた瞬間が、少しずつ増えていきました。
実は他のお母さんにもハビリスをおすすめしたんですけど、やっぱりはじめの一歩が重いように感じます。ニーズが違うなら仕方ないけど、ケアや生活に追われるうちにどんどんすり減っていないか心配で。だからこそ、私のように“偶然出会えた人”もきっかけにして、1日でも早く支援につながってくれたらいいなと思っています。
今の生活はどこか一つ欠けても、ここまでは来られなかったと思います。娘のために動いているのに、いつの間にか“自分の生き方”まで問われるような感覚になって。どう行動すればいいのか、何を信じればいいのか、たくさん悩みました。
でも、ハビリスの皆さんの関わり方を見て、「あ、こういう関わり方でいいんだ」「もっと気楽でいいんだ」って気づけたんです。分泌が多くて、最初は15分の面会でもナースコールを押して吸引をお願いしていたくらいです。でも「娘と家で過ごしたい」…ならやるしかない。いざ帰ると夜は全然眠れない。夫は「こんな状態で家でみるなんて無理だ」と退院当日に諦め、私は病棟で教わった通りにやるしかなく、最後の砦みたいな気持ちでした。
「この子のために、何でも教えてあげたい」と思っていたのに、目の前で苦しそうにしている娘に、呼吸の仕方ひとつ教えてあげられない――あの絶望は今でも忘れられません。よだれを飲み込むなんて、当たり前すぎて考えたこともない。何も教えてあげられないって、泣いて泣いて、毎日が本当に苦しかった。
でも今では、プールに入ったり、ディズニーへ行ったり、高尾山にも登ったり、たくさんの経験をさせてあげられるようになった。それが本当に救いです。医療的ケアって言っても、私たちには“生活の一部”なんだって気づけた今、あの頃の私に「大丈夫だよ」って言ってあげたい。娘にとっても、私自身にとっても、かけがえのない時間を過ごせていると思います。
「道のりは長いので、ぜひ助けを借りてひと休みしつつ、1人では叶えられなかったことを子どもと一緒に叶えていってみませんか。」と伝えたいです。
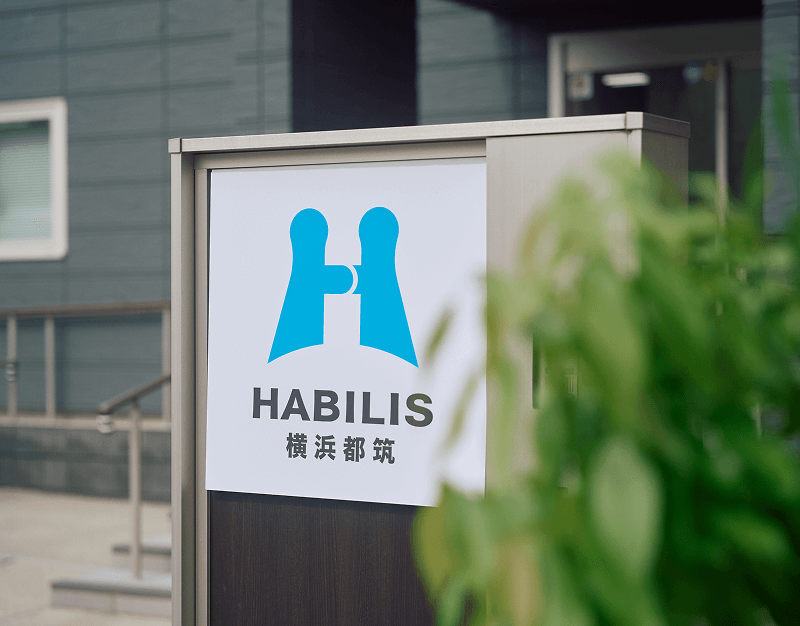
受付時間:月~金 10:00~17:00
(定休日、土日を除く)