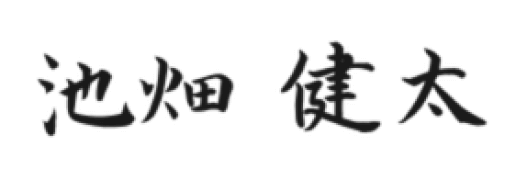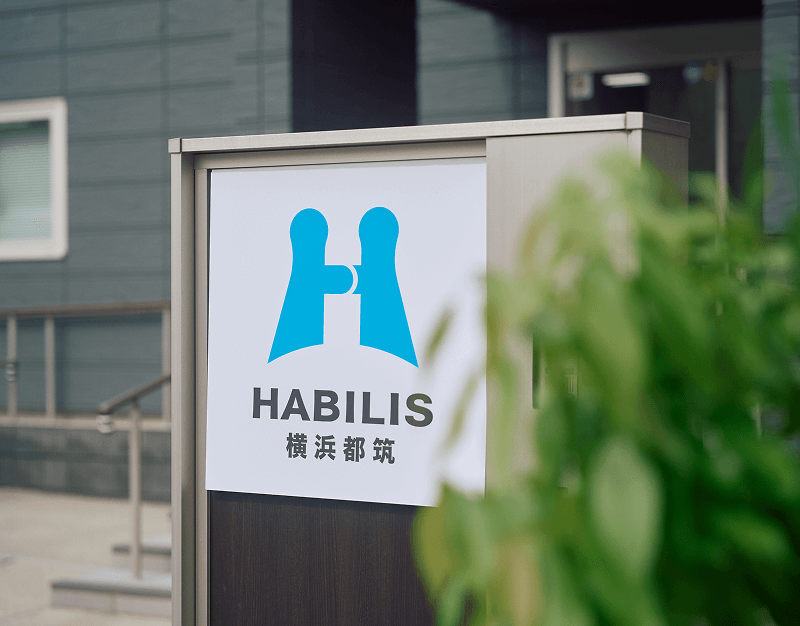私たちHABILISが、なぜこの支援に取り組んでいるのか。どんな未来を描き、
子どもたちとご家族に向き合っているのか。その想いを、代表の言葉でお伝えします。
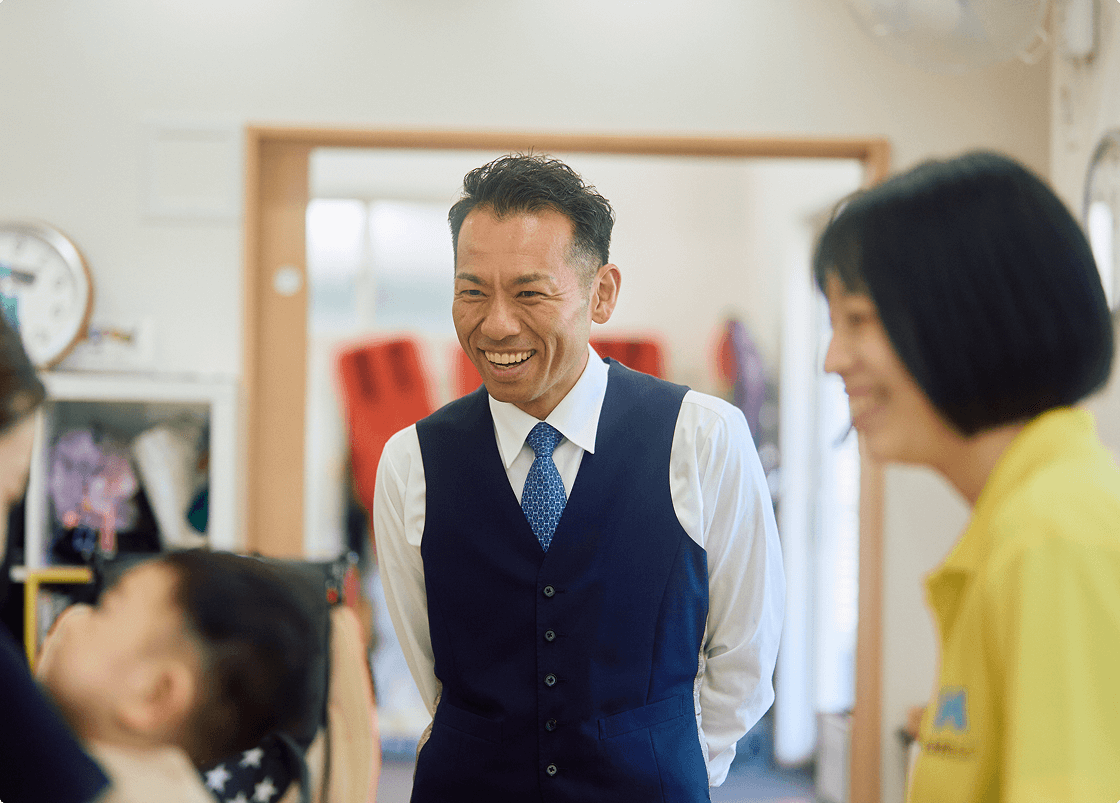
医療的ケア児は10年前から2倍以上に増え、今後も増え続けると言われています。その中で、医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する目的で、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が2021年に施行されましたが、まだまだ家族の負担が大きいのが現状です。その社会的課題を解決するべく、HABILISは医療的ケア児、重症心身障害児を対象とし、様々な事業を展開しています。私が医療的ケア児や重症心身障害児に関わるようになったのは、2017年にある家族との出会いからでした。当時は高齢者向けのリハビリ施設を運営していましたが、ボランティアで障害児のリハビリを行うことになりました。その中で。
「子どもが小学校に上がったらリハビリの数が減ったこと」
「身体のことで困っていることが増えてきたが、相談する場所がないこと」
「それは自分の子どもだけでなく、障害を持った多くの子どもたちが同じ境遇であること」
などの現状を知り、障害を持った子どもたち、そして家族の取り巻く環境が整っていないことで、家族への負担が非常に大きいことを知りました。
「無いなら自分がつくる」
そう決めて、2019年に放課後等デイサービスを立ち上げました。開設すると多くの医療的ケア児や重症心身障害児の方がいるという現実を目の当たりにしました。
「預かってくれて助かる」
「リハビリをしてくれてありがたい」
「仕事をすることができる」
「きょうだいの習い事に付き添える」
など喜びの声をたくさんいただきました。
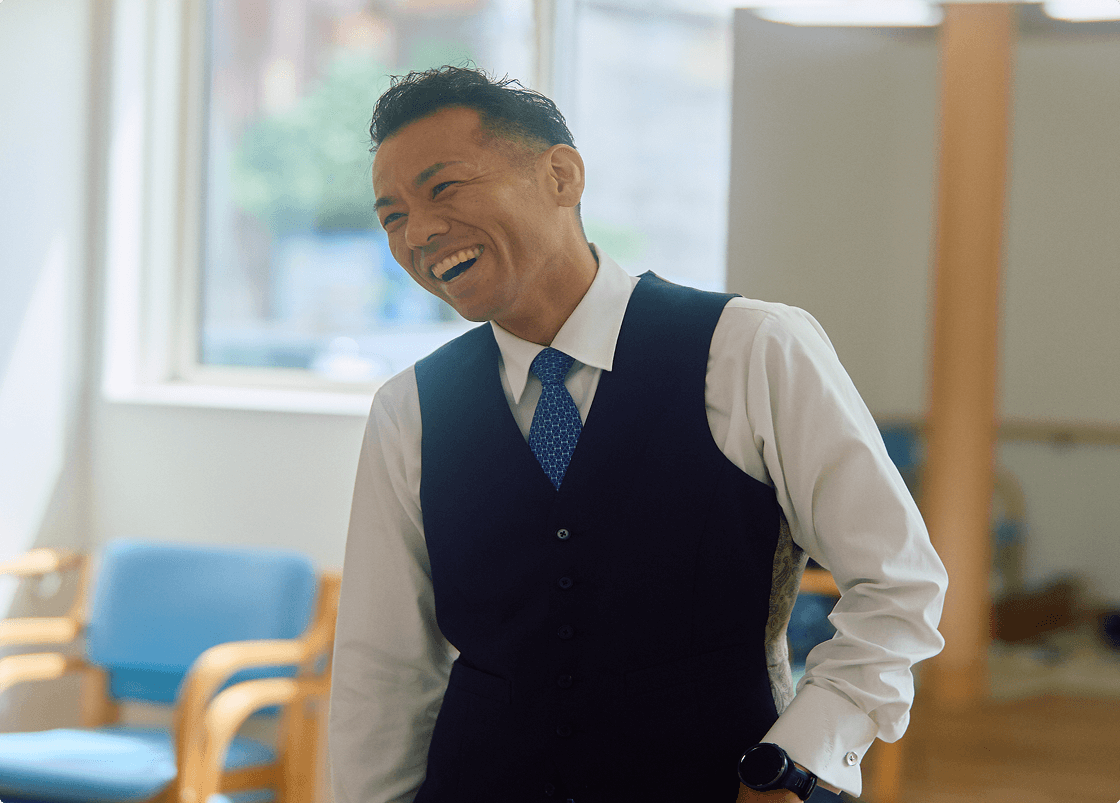
更に私を駆り立てたものは、障害を持つ子どもたちの家族の存在です。
24時間365日ケアをすることが当たり前で、医療的ケア児や重症心身障害児のケアが生活の中心になり、親御さんが仕事をセーブしたり、辞めたり、きょうだい児が習い事に通えなかったり…
子どもたちへの直接的なケアだけでなく、そのご家族にも大きな負担があることを痛感しました。
私には痛いほど分かりました。なぜなら私の兄が障害を持っていたからです。兄は高校生の時に事故に合い、障害を持つことになりました。そこから家族は大きく変化していきました。
兄は高次脳機能障害という脳の障害があり、生活の自立は困難でしたが、身の回りのことは自分でできました。
医療的ケアが無かったので、様々なサービスを受け、何とか生活することができましたが、それでも家族の苦労は大きかったです。
私にはもう一つ原体験があります。私は最初の子どもは死産でした。妻のお腹の中で亡くなりました。今の医療なら助かっていたかも知れない。障害を持っていたかもしれない。
もし兄や自身の子どもが助かって医療的ケアがあったとしたら、どんな生活になっていたのだろうか…?
私には想像がつきませんでした。
子どもが生まれる時は障害を持って生まれるということを想像する人はいません。子どもが生まれたらこんなことをしよう、あんなことをしようと思っていたはずです。それができない中で、精一杯子どもたちのケアをしているご家族の姿を間近で見てきました。
そのケアを私たちが担うだけでも、家族に余裕が生まれてきます。
私たちの存在があることで、ご家族がご家族の人生を豊かにすることが出来る。存分に働いたり、習い事をしたり、趣味をしたり、行きたいところに行ったり、食べたいものを食べたり。
人が当たり前に経験することができることも、障害のある子どもの家庭では当たり前ではないこともたくさんあります。
だから、私たちは子どもたちへのケアの質はもちろんのこと、それ以外の取り組みも積極的に行っています。
ディズニーランドに行ったり、登山をしたり、ヘアカットをしたり、プールに入ったり…
先日は七五三とお宮参りをしたことがないという医療的ケア児のご家族のために、袴や着物を着て写真撮影会を実施しました。
その時のご家族の嬉しそうな表情は、私たちスタッフにも伝播していき、私たちは感謝の気持ちでいっぱいになりました。
みなさんの「できない」を「できる」に変えていくことが私たちの使命です。
すべては、子どもたちと家族の「できる」をつくっていくために、私たちは存在しています。